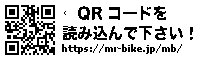1990年7月29日、真夏の祭典 ’90 FIMエンデュランスカップ第2戦“鈴鹿8時間耐久ロードレース”は、平 忠彦/エディ・ローソン組のヤマハYZF・TECH21が圧倒的な強さを見せつけた。30度を超える炎天下のもとで、予選をクリアした65台が、それぞれの熱く激しい闘いを続けていく。ある者は転倒で戦列を去り、ある者はマシントラブルに見舞われてピットに長時間釘付けにされる。ガス欠という予想外のトラブルに見舞われたガードナー/ドゥーハン組のように、8時間のスプリント耐久レースは様々なドラマを巻き起こす。蒸し暑い鈴鹿の夏は、ライダーにとってもあまりにも過酷なステージ以外のなにものでもない。
レースはチェッカーを受けるまで何が起こるか全く予想できない。13500rpmキープ、ギリギリの高回転の連続の果てに、ラスト30分で息絶えたマシンはあまりにも多い。’85年、5バルブのヤマハFZRはゴール35分前にマシントラブルに見舞われ、’87年にはヨシムラGSX-Rの高吉克朗/ギャリー・グッドフェロー組が、7時間55分までトップを疾走していたにもかかわらず、ラスト5分の転倒劇で2位に甘んじた。
TECH21が挑戦6シーズン目にして初の勝利を確信した頃、夕暮れのシケインでオイルフラッグが激しく振られた。19時12分、ゼッケン12
ダグ・ポーレン/ミゲール・デュハメル組のヨシムラGSX-Rは白煙を吹上ながらストレートを通過、明らかに1気筒が死んでいる。それでもダグは3気筒になってあえぐマシンを労りながら走行を続け202周をクリア。6位という充分すぎるリザルトを残した。
写真はその8耐を戦い抜いたGSX-Rの破壊されたピストンである。おそらくバルブ周辺のトラブルが原因であろうが、かの美しいヨシムラチューンのピストンは、破壊されたパーツやバルブに叩かれ続けながらも、残り18分をレーススピードで闘い抜いた。
致命的とも言えるトラブルを抱えたマシンをゴールに向けて走らせる勇気とは一体何だろうか。
運が悪ければリタイア、最悪のシナリオはコンロッドがクランケースを突き破り、コース上にオイルをぶちまけ息絶える。ダグ・ポーレンは一時10秒ほどペースを落としたのだが、すぐに回復して残りの周回を淡々と走り続けた。
「ラッキーでしたね」ヨシムラを率いる吉村不二雄氏は、当時を振り返ってこう言い切った。万一ピットインでもすればエンジンの再始動は困難であろう。「GO」のサインは出したが、結局最後の判断はダグにゆだねられた。多分それは信頼のなせる業だったのだろう。傷ついたマシンをゴールラインまで運んだダグとヨシムラにとって、’90年8耐の6位は“価値ある6位”として永遠に語り継がれるべきだろう。
写真のようにピストン頭部は傷だらけだった。アルミホイルをくしゃくしゃにしたような、見事なまでの破壊の痕跡だ。もちろんトラブルによって変形したものだが、ピストンリングから生き残っていた。コンロッドもピストンピンもOKだった。ピストン頭部の削りかすの大半はエキゾーストポートからきれいに排出されてしまったという。わずかにクランクケースの下部に落下したアルミ片も致命傷を負わせずにいた。そんな偶然の重なりもまた、レースマシンの熟成のヒントになる。
ヨシムラのレーシングピストンは好んで鍛造ピストンが使われる。強度に優れ、熱変形の少ない鍛造によるピストン製作。一説には13500rpm時に250gのピストンの慣性質量は軽く1トン半を越えるという。そのためには鋳造されたものより鍛造品のほうが明らかに強度、熱に対して有利だ。と言っても、鍛造ピストンを使い出したのは’81年のGSX1100Sから。’78年、’81年と二度鈴鹿8耐を制した空冷2バルブのGS1000には、意外にも鋳造ピストンが用いられていた。
だからピストンが割れたり、トラブルも多かった。鍛造品に切り替えた当時も、初期には軽量化をしすぎたり、形状の煮詰めが甘かったりで、テストする度に壊れた。鍛造は強い。だが、強いからといって何をしてもいいというわけではない。壊しながらデータを蓄積していった。“I’ve Got the POWER”の面目躍如である。
パワーを引き出せばストレスは弱い部分に襲いかかる。より軽く、より強くバランスさせなければ高性能エンジンは生まれてこない。
爆発圧力を常に受け続けてパワーの源泉となるピストン部は、シリンダーヘッドの形状、バルブの大きさによって頭部のファインチューニングを受けるのだが、十分な圧縮比を得るために旋盤やフライス盤によってヨシムラの手による加工を受ける。バルブとクリアランス、燃焼形状、燃焼室容量と微に入り細に入りチューニングが施されていく。
油冷GSX-Rのヨシムラマシンは、2年前の段階で140〜145psを絞り出し、時には14000rpm以上の高回転で酷使され続ける運命に耐え続けていった。
ヨシムラの芸術的なチューニング術はマシンのあらゆる部分に施される。パーツ単体、例えばピストンだけが突出して評価されることはない。すべてのパーツが組み合わされた状態での評価になる。“馬力を落とさず効率のよい仕事をする”レーシングエンジンに求められる数々の要求をクリアしてエンジンという生命体になって初めて評価がなされるのだ。ピストン製造はピストンメーカーで、軽量化やピストン頭部の加工はヨシムラ独自のノウハウを総動員するという手法は今に始まったわけではないが、テストを重ね、バラすごとに状況判断し、効率を判断し、各部の測定を繰り返す。こうした水面下の地道な努力が、チューナーとしての“ヨシムラ”の名声を今に継承しているのだ。
「ピストンの頭を見れば、だいたいどのくらいパワーが出ているかわかる」
バルブの逃げを滑らかにして、かつ表面積を小さくする。ピストン裏の肉抜き。クリアランスとさまざまな加工ひとつひとつにヨシムラの思想がたたき込まれていく。さらにテストを繰り返し、ピストン頭部のカーボン堆積の状態で燃焼状況が確認される。黄金色になったピストン頭部が、良好な燃焼状態であることを雄弁に伝えてくれるのだった。
‘92年、ヨシムラは水冷化されたニューGSX-Rベースのマシンを大阪賢治と青木正直の二人に託して全日本ロードレースF1クラスに参戦中だ。シーズン前の熟成の過程では、当然のことながらエンジン各部の徹底的なチェックが重ねられた。開幕戦鈴鹿2&4で2位入賞。ヨシムラ復活への確かな手応えを感じた。
走り続けるヨシムラも活躍の裏には、数々の経験が活かされている。